2018年04月23日 作成 / 執筆:Lucky Ocean講師

二次試験にチャレンジする人へ
皆様はもう受験票を出しましたか?正直、悩んでいる人もいらっしゃるのではと思います。
私も4部門目のチャレンジをしようかどうかずっと悩んでいます。昨日、なんとか、受験票
を作成したけど、今お財布にキャッシュが1万円しかないので、郵便局に行く前にお金を
下ろさねば。その前に写真が必要だ。今日は無理だなあ。明日にしよう。
そんな風にギリギリになって提出する人も多いかもしれない。でも、最初の受験の時は気合い
が入っていて、3月中には受験票の内容を精査して、4月の受験票申し込みの受付開始早々に
申込書を送付しました。
早く出せばその分、早く筆記試験への勉強を本格的に開始できるので有利なのは間違いない。
でも、無理に急いでも内容が不十分だったり、ミスがあると意味がない。早く出そうとギリギリに
出そうと大切なことは、7月15日の筆記試験に向けての勉強にギヤチェンジすることです。
具体的な勉強方法については、これからシリーズで書いていきたいと思います。
対策1)必須科目I(択一問題)への対応
対策2)選択科目II(記述問題)への対応
対策3)選択科目III(記述問題)への対応
私も覚悟を決めるので、一緒に頑張っていきましょう!
2018年06月30日 作成 / 執筆:【ニュース担当】eastwest665講師
技術士試験では、口頭試験や記述式試験など、今まで勉強したこと成果を十二分に発揮することができない場合が出てくることがよくあります。
そんな時に、分からない試験に当たっても、挽回できるよう度胸をつけたいと考えている人が意外と多いのではないでしょうか?
度胸があれば、この試験がダメでも次があるという前向きな気持ちにもなりやすくなります。
今回は度胸をつけたい時に聞きたい名言を集めてみました。
そもそも度胸とは?
多くの辞書を引くと、度胸という言葉の説明に、「物事を恐れない心」とあります。
技術士試験を恐れない心を持つことは、事前の試験勉強などをこなし、天命をまつような状態になっていればつけることができるものと考えられます。
あとは何が来ても後悔しないという状態のことを度胸があると言い換えることができます。
度胸さえあれば、不可能はない。
JKローリング
ハリーポッターシリーズの原作者として知られているJKローリングの言葉です。
一時期は生活保護を受けながらも、小説を書き続けたことで知られている苦労の人です。しかし、最終的には世界中で大ヒットをしたシリーズを書き上げることになります。
そんな原作者でも、やはり度胸は重要と考えているようです。
度胸が欲しければ、恐ろしくて手が出ないことに挑んでみることだ。これを欠かさずやり続けて、成功の実績を作るのだ。これが恐怖心を克服するための最も迅速でしかも確実な方法である。
デール・カーネギー
自己啓発や成功哲学に関する書籍を多く執筆しているアメリカの作家、デール・カーネギーの言葉です。
難しい試験にはできなかったらどうしようという恐怖がつきまとうものです。それは不合格になったらどうしようと考えることにつながります。
こうした恐怖心を克服するためにもまずは挑戦してみることが重要だと説いています。
そのためには、練習問題や試験勉強はその前段の対策となります。そのうえで恐怖心を克服することで度胸がついていくのではないでしょうか?
2018年07月23日 作成 / 執筆:タートル講師
平成30年度技術士第二次試験の試験問題が公表されました。
建設部門の河川、砂防及び海岸・海洋科目の試験問題について、出題の解説や記述すべき方向性を述べます。
以下はⅡ-1-3に関する記述です。
Ⅱ-1-3は砂防に関する問題で、土砂災害に対する警戒避難体制を問う内容です。
問題文の中に「要配慮者利用施設」という文言がありますので、平成29年6月に改正された「土砂災害防止法」
の内容を踏まえた記述をすることが重要です。
問われているのは以下の2点です。
①対象とする土砂災害の種類と特性、その被害を防止・軽減するための警戒避難体制整備にあたっての留意事項
②要配慮者利用施設の管理者等が避難計画を作成する際に記載すべき事項を2つ以上
まず①についてです。
問題文を批判するわけではありませんが、2通りの解釈ができそうです。
土砂災害防止法において「土砂災害」は、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り、河道閉塞による湛水の4つですが、
警戒区域の指定に基づき市町村が警戒避難体制等の整備を行う必要があるのは前者3つの災害(急傾斜地の崩壊、
土石流、地滑り)です。
1つ目の解釈は、これら3つそれぞれに関して特性を説明して、そのうえで土砂災害全般に関する警戒避難体制整備
にあたっての留意事項を述べる、というものです。
2つ目の解釈は、3つの災害いずれか(例えば土石流とします)を取り上げ、土石流災害の特性を説明して、その
うえで土石流に対する警戒避難体制整備にあたっての留意事項を述べる、というものです。
個々の災害形態に特化した警戒避難体制というのは、かなり難易度の高い設問だと思いますので、素直に解釈すれば
1つ目の解釈で記述する方が自然かと思いますが、2つ目の解釈で記述しても間違いとは言えないと考えます。
次に②についてです。
これは土砂災害防止法の施行規則(第五条の二)に、計画に定めるべき事項が挙げられていますので、そのまま以下に示します。
一 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における防災体制に関する事項
二 急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の避難の誘導に関する事項
三 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
四 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ
迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
5つ目は、「その他必要な措置」ということですから、防災体制、避難の誘導、施設の整備、防災教育及び訓練の実施、の4つの中から
2つ以上を挙げて具体的な内容を記述していれば題意を満たした記述となります。
*各種対策講座を行っています。講師ページから詳細を記したファイルをダウンロードできますのでご覧ください。
2018年07月24日 作成 / 執筆:【ニュース担当】eastwest665講師
技術士試験を受験しようと考えている人にとっては常識であっても、初めて受験をするような人にとっては馴染みの薄い技術部門というものがあります。
技術部門は20からなる多くの専門分野が細かく分かれています。
その技術部門の中でもさらに専門分野別に分かれており、技術士と一口に言っても様々なバックグラウンドを持った人が多く在籍するのが技術士の集合体である技術士会であると言えます。
そんな技術部門を一つずつ紹介していこうというものが今回からの企画です。
是非技術士を受験しようと考えている若い方にも読んでいただきたいと思います。
技術士 機械部門の概要
技術士の機械部門は主に機械設計を行う人向けの技術士資格と言えます。
受験時の専門科目も機械設計や材料力学、熱工学、流体力学など大学の機械工学を専攻している人であれば必ず習得するような内容のものが多く含まれています。
また、その一方でロボットやファクトリーオートメーションなどの機械分野と電気分野の複合分野である制御系の専門科目も選択できるようになっております。
技術士 機械部門取得後の活躍
技術士の機械部門は機械設計を行う仕事や研究開発などに技術士を活かすことができます。一例としては自動車メーカや工場で稼働する産業機器メーカ、ロボットを扱うメーカなどで開発、設計職として技術士の機械部門を活用することが可能です。
技術士 機械部門の問題点
技術士全般に言えることではありますが、機械の設計は、設計ミスなどが事故につながる重要な職種でもあるにかかわらず、設計職に従事するための公的な資格が存在しません。技術士は設計、開発を行う資格ではあるのですが、法的に設計職に必要な資格ということではないため、取得していない人も多くいます。
機械の設計に関わるための必須資格ではないことで、技術士機械部門の知名度も大きくないことが一番の課題です。
しかし、その試験内容の専門性の高さと、実務経験の証明にもなるため、昇進や転職時のインパクトとなるのではないかと思います。
2018年12月09日 作成 / 執筆:技術サムライ講師

業務経歴票や筆記試験では、日本語のルールを守って書きます。技術士試験は、記述量が多い試験ですから、この当たり前のことが、とくに重要になります。
句点と読点は、文脈を明らかにします。また、文を正しく、かつ容易に理解できるように打つものです。
1.「。」句点(くてん)
(1)文の終わりに必ず打つ
(2)箇条書き、タイトル、項目名には打たない
(3)通常は、( )、「 」の中の最後の文末にはつけない
(○)日本語のルール(現代表記法) (×)日本語のルール(現代表記法。)
ただし、3.について、( )書きで注釈を入れる場合は、( )の後に句点を打ちます。
(例)技術士とは、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価、又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行うものをいう。
(出典:技術士法第2条)
2.「、」読点(とうてん)
(1)主語をはっきりさせるために打つ
(2)文の切れ目、前後の関係をはっきりさせるために打つ
(3)接続詞、副詞のあとに打つ
(4)条件文のあとに打つ
(例)なお、生態系の観点からも検討が必要である。
(例)しかし、当該案は費用が2倍に増える。
(例)目的が工事費の提言であることから、施工計画が重要となる。
「このような当たり前のことを?」と思わず、意識して、作文してください。
なぜなら、技術士試験では、「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」が試されているからです。
このコンピテンシーの8項目のなかに、「コミュニケーション」があります。
そして、コミュニケーションには、「業務履行上、口頭や文書等の方法を通じて、雇用者、上司や同僚、クライアントやユーザー等多様な関係者との間で、明確に効果的な意思疎通を行うこと」と書かれています。
つまり、文書で明確に意思疎通が行うために、句点や読点を適切に使うことも必要なのです。
2019年02月04日 作成 / 執筆:スチールマニア講師

受験生の中で合格する人の特徴として以下の3点が共通していることに気づきます。
・素直な人(言われた事をすぐに実践する人)
・何事にも積極的であること(行動が速い)
・人のネットワークが広いこと
素直な人は、教えられたことを自分の中で理解し、合格するために真似をすることを始めます。
教えられたことを素直に実行に移すのです。
逆に、教えられたことに対して反抗的な人は、自分はそう思わないと考えたり、
同じやり方は嫌だと考えたりしてしまいます。結局、悪い部分を直さずに、実行に移すこともできないのです。
教える方々は、自分の経験をもとに合格するためにはどうしたら良いか?を伝えています。
受験生を落とすことを考えて発言する人はいません。まずは素直になることが大事です。
また、周りに何をやってもうまく立ち回る人、結果が付いてくる人、要領がいい人がいると思います。
そのような人に共通する事は、積極的に行動し、人材ネットワークも広いことが挙げられます。
資格試験において、膨大な知識を限られた時間で頭の中に詰め込むことは、時間と効率が大事になります。
時間が大事なのに、すぐに行動しなければもったいなくないですか?
また、近くに資格試験を経験した方が居れば、様子を聞けばいいんです。
勉強方法はどうしたか?時間の作り方は?教材は?などと質問すればいいんです。
それは、ズルでも何でもなく、効率が良いやり方です。
まず、受験したいという資格があるならば、素早く行動に移してください。
そして廻りの方々の経験をうまく利用してください。更に、それらの情報に対して素直になってください。
合格する為には、これらのことが大事です。
2019年02月25日 作成 / 執筆:スチールマニア講師

受験生の方から、択一問題から筆記問題に変更されるが、どのような対策をしたら良いか?
というご質問を頂くことがあります。
今回が初めての試みですから、これが正解という対策はありません。
しかし、どのような出題がなされ、どのようなポイントが評価されるのか?
を知ることはとても大切なことです。
日本技術士会HPに技術士2次試験の変更点と出題内容、評価項目が記載されたものがあります。
以下にURLと抜粋を載せます。
平成31年度技術士試験の概要について
https://www.engineer.or.jp/c_topics/005/attached/attach_5698_1.pdf
Ⅰ. 必須科目
|
概念 |
専門知識 専門の技術分野の業務に必要で幅広く適用される原理等に関わる汎用的な専門知識 |
|
応用能力 これまでに習得した知識や経験に基づき,与えられた条件に合わせて,問題や課題を正しく認識し,必要な分析を行い,業務遂行手順や業務上留意すべき点,工夫を要する点等について説明できる能力 |
|
|
問題解決能力及び課題遂行能力 社会的なニーズや技術の進歩に伴い,社会や技術における様々な状況から,複合的な問題や課題を把握し,社会的利益や技術的優位性などの多様な視点からの調査・分析を経て,問題解決のための課題とその遂行について論理的かつ合理的に説明できる能力 |
|
|
出題内容 |
現代社会が抱えている様々な問題について,「技術部門」全般に関わる基礎的なエンジニアリング問題としての観点から,多面的に課題を抽出して,その解決方法を提示し遂行していくための提案を問う。 |
|
評価項目 |
|
Ⅲ. 選択科目
|
概念 |
社会的なニーズや技術の進歩に伴い,社会や技術における様々な状況から,複合的な問題や課題を把握し,社会的利益や技術的優位性などの多様な視点からの調査・分析を経て,問題解決のための課題とその遂行について論理的かつ合理的に説明できる能力 |
|
出題内容 |
社会的なニーズや技術の進歩に伴う様々な状況において生じているエンジニアリング問題を対象として,「選択科目」に関わる観点から課題の抽出を行い,多様な視点からの分析によって問題解決のための手法を提示して,その遂行方策について提示できるかを問う。 |
|
評価項目 |
技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)のうち,専門的学識,問題解決,評価,コミュニケーションの各項目 |
この表から、必須科目と選択科目Ⅲは非常に似ていますが、
評価項目で必須科目Ⅰには「技術者倫理」が入っていますが、選択科目Ⅲには入っていません。
この表から推察できることは、
必須科目では「技術者倫理」に関する社会的認識について、述べさせたり、
受験する技術部門において、公益確保に反する過去の事故・不正トピックの事例を挙げさせ、
自分の考えを解答させたりが考えられます。
すなわち、技術者倫理に関することを整理してしまえば、
後は、選択科目Ⅲに必要な専門とする事項のキーワードについて勉強すればよく、
今までと変わらないということになります。
技術者倫理は口頭試験でも必ず聞かれることですし、今の内からまとめておきましょう。
2019年03月21日 作成 / 執筆:【ニュース担当】eastwest665講師
技術士 生物工学部門の概要
日本酒や焼酎や漬物など、微生物による発酵を利用した食品は多く生産されています。
酒類や漬物などは和食として海外でも高品質な食材として輸出されるケースも増えています。
また、下水処理などでも浄化槽に微生物を投入して汚れを分解させるような技術も確立しており、実際に多くの下水処理場で微生物による浄化槽が導入されています。
食品の発酵を分析し、食品生産の効率化を行ったり、長持ちさせるための措置を講じたりする食品生産の技術者や微生物を用いた環境浄化を行う技術者のための部門が技術士環境部門です。
専門分野は遺伝子に関する内容を問う細胞遺伝子工学、生物を使った応用分野を問う生物化学工学、生物を使った環境関連の内容を問う生物環境工学の三分野です。
技術士 生物工学部門取得後の活躍
発酵を利用した食品メーカなどの生物関連のスペシャリストとして働くことができます。
生物を利用した環境浄化に関する企業などにも需要があります。
また、求人数は少ないですが、生物関連の研究所などでも技術者として働くこともできる道があります。
技術士 生物工学部門の問題点
技術士生物工学部門の問題点は、受験者数の少なさにあります。
受験者数は50人以下の年もあり、技術士の専門分野の中でも少ない部類に入ります。
また、生物関連の資格を取得するというよりは、博士号を取得する人の割合が多く、研究分野としてまだまだ未知の部分が多いものとなります。
試験の内容も医師や看護師などの分野とも重複するような部分もあり、医療系の資格として取得するにはその先の働き口がないという非常に中途半端な印象を受けます。
食品メーカなどでも、特に技術士がなければ仕事に従事できないということではないということも、受験者数が増えない要因となっています。
技術部門の受験者数は、今後の統廃合の動きにも大きく関わってきますので、注意してみておく必要があります。受けたい技術部門がなくなるということもあるかもしれません。
2019年03月30日 作成 / 執筆:Lucky Ocean講師

勉強と研究の違い
勉強とは自分は知らないけど世の中では既知な知見を得ること。教科書で学ぶことは学習だ。一方、研究とは、世の中でも未知な知見を得ることだ。教科書を新しく作ることは研究と言えるだろう。
技術士になるには学習が必要
技術士の過去問題は公開されている。こんな問題が出るよと前もって見せてくれている。なので、こんな問題が出たら、こんな風に解答しようと準備しておけば良い。これがいわゆる技術ノートだ。自分の場合には、重要そうなテーマを100個ほど集めて、それに対して、そのキーワードの概要=特徴と、課題と、その課題への対策をA4でまとめる。そして、その技術ノートを見ながら、600字の原稿用紙に特徴とか課題を書くドリルをする。原稿用紙にうまくかけた時にはそれを技術ノートにフィードバックして改善する。逆に原稿用紙にうまく書けないときは、そもそも技術ノートが行けていないので、補強する。これを3回ぐらいやると、かなり使える技術ノートになるし、まとめるべきキーワードがどんどん増えてくる。
技術士になったら研究にシフト
技術士試験に合格した後も、技術ノートを磨くべきという人もいる。しかし、より重要なことは、それまでに学習した内容をベースにしてもっと深堀すべきだと思う。自分なりに解決できるような社会的な課題を探したり、技術動向を調べたりすることと、それをアウトプットすることだ。学会でもいいし、ブログでもいい。大事なことは色々な新しいことに興味を持ち続けることだろう。自分も分からないことがあるとまずWikiで調べるが、どんどん深く調べていくと、最後はWikiに書かれていないことにたどり着くことがある。Wikiに書かれていることを調べるのは学習だけど、Wikiに新しい内容を書き込むことは研究活動の一つと言えるのではないだろうか。
まとめ
技術士は実社会の課題を解決することがミッションだ。そのためには、勉強は必要だが、それだけでは不十分だ。やはり研究することが必要だ。そして、研究成果を上げるには、テーマ選定が重要だ。どんなテーマを設定するかは、やはり自分が好きなこと、興味のあること、求められていることが候補だろう。個人的には、好きなことを好きなだけ研究し続けるのはワクワクするし、楽しい。そして、それが他人にも認められて、後追いで自分の仕事になることはなんども経験した。あなたも技術士になってワクワクしながら社会的課題を解決しませんか。
以上
2019年04月05日 作成 / 執筆:技術サムライ講師

総監の試験では、とにもかくにも、総合技術監理が必要とされる背景を押さえることがとても重要です。
『技術士制度における総合技術監理部門の技術体系』(第2版)、いわゆる青本には、次のように記されています。
『科学技術の発達により人々が享受する恩恵は、日々の生活の中に浸透している。
しかしその一方で、科学技術の巨大化・総合化・複雑化が進展しており、その発達を個別の技術開発や技術改善のみによって推進することは難しい状況になりつつある。
つまり、科学技術の発達を推進する業務は一部の専門家のみによって完結するものではなく、さらに言えば科学技術は単独でその有効性や価値が生じている訳でもなく、企業などの組織活動が技術の有効性を発揮するための大きな基盤となっている。
また、それに伴って事故や環境汚染などが発生した場合の社会への影響も、従来に比して遥かに大きなものとなっている。』
この文章は、『総合技術監理 キーワード集 2019』にも記されています。
ここでのポイントは、次の2つです。
①科学技術が複雑になっているため、もはや一般部門の技術者や専門家だけでは、プロジェクトを始めから終わりまでやり遂げることができないこと
②ひとりひとりの技術者等を束ねるスキルがある人材が求められていること
そこで、受験生のみなさんは、そのスキルを有していることを筆記試験と口頭試験で、採点官に評価してもらえるように準備してください。
具体的には、5つの管理技術を使いこなし、業務を俯瞰的に見渡して、全体最適化をはかって、首尾よく業務を完遂させるスキルです。
総合技術監理部門は、たしかに合格率が低く難関ですが、総監が必要とされる背景、総監で求められているスキルを押さえることで、きっと合格率が高くなります。
2019年04月07日 作成 / 執筆:技術サムライ講師

技術士会HPで公開されている過去問(平成21年度~平成30年度)をもとに、法令問題を抽出し、「年度」と「5つの管理」(経済性管理、人的資源管理、情報管理、安全管理、社会環境管理)ごとに分類したところ、つぎの3つの傾向が明らかになりました。
(1)最近5年間では、択一式で出題される40問中8~10問(20%以上)で法令問題が出題されている。
(2)経済性管理を除く4つの管理では、ほぼ毎年、法令問題が出題されている。
とりわけ、人的資源管理と社会環境管理では、法令問題の出題割合が多く、年度によっては、出題数の半数が法令に関するものである。
(3)出題される法令は繰り返し出題されるものが多い。
具体的には、人的資源管理では労働基準法、情報管理では個人情報保護法、安全管理では労働安全衛生法、社会環境管理では環境影響評価法が頻出です。
なお、内容面では細部を問う論点が増え、法令問題対策の重要性が高まってきています。
そこで、まず、法令対策にかける時間を確保しなければならないと覚悟します。そのうえで、つぎの手順で対策するとよいでしょう。
(1)技術士会HPから過去問をダウンロードし、法令問題の5つの選択肢ひとつずつで、正しい選択肢であるか、誤った選択肢であるか判断できるようにする。
(2)正しい選択肢についてはその問題文を、誤った選択肢については、誤っている箇所を訂正した問題文を暗記する。
(3)(3)について、今後、出題されそうな論点を予想する。
一般に、法令問題では、混同しやすい法律や、用語を入れ替えたり、数字を変えたりして間違った選択肢を作ることが多い。
(4)総合技術監理キーワード集2019に挙げられた未出題法令の目的条文等を読む。
受験申込書の提出が終わったら、択一式対策に取り組みましょう。
2019年04月15日 作成 / 執筆:タートル講師
4月8日から、技術士第二次試験の受験申込受付が始まっています。最終締切は4月24日なので、
受験申込書の内容を推敲中の方も多いと思います。
ここでは受験申込書を提出する前にチェックしておくべき事項を紹介したいと思います。
1.受験する部門・科目がメインの内容となっているか
5つの業務経歴は、受験する部門・科目の内容がメインになっているでしょうか?また、「業務
内容の詳細」は、課題や解決策を受験する部門・科目の切り口で記述できているでしょうか?
業務経歴については、「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、
研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導」であるとともに、受験する部門・科目の内容
がメインになっていることが重要です。例えば建設部門の道路科目を受験するのに、道路に関する業務
は1つだけで、残りの4つはトンネルに関する業務というような内容だと、口頭試験の時に厳しい質問が
来ると考えましょう。
「業務内容の詳細」については、題材もさることながら、課題や解決策が受験する部門・科目の切り
口になっていることが重要です。例えば道路が対象であっても、課題や解決策が軟弱地盤対策に関する
ことであれば、土質及び基礎科目と見なされる可能性が高くなります。
「部門・科目のミスマッチ」があると、口頭試験でリカバリーすることは非常に難しくなります。
提出前に適切な内容となっていることを確認しておきましょう。
2.年号は西暦で書いているか
5月の改元に伴うことかと思いますが、今年度から年号は元号ではなく西暦で記載することになって
います。細かい変更ですが、決められたルールに従った記載が必要です。
3.業務経歴の合計年数は記載した業務のみの合計となっているか
「合計年数の欄は①在学期間(上限2 年)及び②従事期間の合計年数を記入する」ことになっています。
従来は業務経歴を一部省略した場合でも、省略した期間も合計年数に加えることができましたが、今年度
からは省略した業務経歴の年月数を合計に加算しないことになっています。
4.業務内容の詳細の文字数は720字以内になっているか
受験申込書の「業務内容の詳細」欄の仕様が変更されています。従来は「720字のスペース内に入力」
だったので、せいぜい700字前後しか記載できませんでした。新たな様式では「900字のスペースに720字
以内で入力」なので、実質的には記載できる文字数が増えたと言えます。
提出前にWordの文字数カウント機能を使う等、720字以内で記述しているか確認しておきましょう。
*各種対策講座を行っています。講師ページから詳細を記したファイルをダウンロードできますのでご覧ください。
2019年06月02日 作成 / 執筆:スチールマニア講師

数多くの論文を添削すると、論文の執筆方法のルールを勉強した方がいいと感じる方が多くいます。
もっとも大事なことは、出題文を読み解き、聞かれている事項にしっかりと答えるということです。
具体的な例を挙げます。
問題文(1)である事象の背景とその背景から考えられる問題点を挙げよ。
問題文(2)で、その問題点から解決すべき課題を挙げよ。
という問題があったとします。
ここで、問題点と課題を同じことだと考え、(1)で挙げた問題点を、
そのまま課題として挙げる方が非常に多くいます。
あえて、問題点と課題を異なる問題文で問われているのですから、
それぞれに合う表現で記述しましょう。
問題と課題をそれぞれ辞書で調べてみます。
問題
①問いかけて答えさせる題。解答を要する問い。
②研究・論議して解決するべき事柄。
課題
題、または問題を課すること。また、課せられた題、問題。
辞書の意味だと、ほぼ同義として受け取れます。
しかし、ビジネスシーンではこの二つの言葉をはっきりと使い分けているのです。
問題:ネガティブな影響を及ぼすもの(ネガティブな表現)
課題:ネガティブをポジティブに変換するために成すべきこと(ポジティブな表現)
と分ければ、非常にわかりやすいでしょう。
具体例を挙げます。
<背景>
少子高齢化が進み、日本の人口は減少の一途をたどっている。
しかしながら、東京オリンピックやリニア新幹線などのビッグプロジェクトが進行中であり、
進めるべき業務が多い。働き方改革により、業務時間が制限されるなどの制度もある。
<問題点>(ネガティブな表現)
・技能労働者の減少
・工期遅延
<課題>(ポジティブな表現)
・生産性を向上させる
いかがでしょうか?働く人が減り、働く時間が減り、その結果工期が遅れてしまうという
ネガティブな状況を、生産性を向上させるというポジティブな思考で、解決できないでしょうか?
そして、この後に続くのが、課題を実現させるための具体的な解決策を示すのです。
このように、問題文にある言葉の意味を正確に把握し、
解答すべき内容にズレがないように記述しましょう。
2019年06月08日 作成 / 執筆:技術サムライ講師

勉強場所をいくつか確保しておくと、勉強がはかどります。自宅の書斎、図書館、喫茶店やファミレス、通勤電車など。
以下に、それぞれのメリットとデメリットを書きましょう。
自宅(の書斎)は、メインになる勉強場所です。本棚にある書籍を参照したり、パソコンで調べ物をしたりして、腰を落ち着けて勉強できる場所です。
一方で、小さなお子さんがいる場合には、しばしばその相手をする必要があり、勉強が途切れ途切れになってしまうといった難点があります。
近所の図書館は、昔から人気のある勉強場所です。一般的な家庭よりも充実した書籍類が自由に使えます。そして、高校や大学受験の対策をしている学生や、他の資格試験の受験生とともに、比較的、静かな環境で、自習することができます。
一方で、他の利用者に、ライバル心が生まれてしまい、勉強後には疲労感が溜まってしまう場合があります。
会社近くの喫茶店は、平日の勤務前や退勤後に使えるので便利です。たとえ、15分や20分でも地道に勉強を積み重ねれば、成果が確実に現れます。
喫茶店の良いところは、同じようなサラリーマンが資格勉強をしていることです。彼ら彼女らには、図書館の利用者にありがちな悲壮感があまりないところも良いところです。
また、休日の午前中の喫茶店やファミレスには、シニア層がリラックスして時を過ごしています。こちらも、日常業務の疲れを癒やしながら、気分穏やかに勉強するのに適しています。喫茶店やファミレスでの勉強は、まわりが騒がしいことがあるのと、長居しにくいことがデメリットです。
通勤電車は、時間をもっとも有効利用できる勉強場所です。移動の無駄な時間を勉強にあてられるのがメリットです。習慣にできると良いでしょう。
ただし、疲れているときもあるでしょうから、行きと帰りのどちらか一方でもできればOKくらいの気持ちでやるのが、続けるコツでしょう。
試験日まで残り1ヶ月、勉強場所を工夫して、納得いくまで対策しましょう。
2019年07月06日 作成 / 執筆:技術サムライ講師

技術士試験は短時間でたくさんの文字を書かなければならない珍しい試験です。今年度からは、必須科目Ⅰの択一式試験が変更になり、600字の原稿用紙3枚の記述式に変わりました。そのため、選択科目Ⅱ、選択科目Ⅲと合わせて、9枚、計5,400文字もの記述が求められます。
技術士試験にはさまざまな記述テクニックが伝えられています。
例えば、シャーペンは、太い軸のもので、グリップ部分が柔らかいものが良いというテクニック。これは、私もぜひおすすめします。当日、試験が終わると、軽く腱鞘炎になるくらいの手指、手首の疲労があるためです。
そのほか、細い軸のシャーペンや、シャカシャカと振ると芯が出るタイプのシャーペンも用意しておくと良いです。これらを持ち帰ることで、ほんのわずかにですが、試験中の気分転換になります。
消しゴムは、新しいものを複数、用意する。これもおすすめです。カドを使って、正確に、すばやく消すために、安い投資と思います。
タイトルと小見出しは、太芯で書き、目立たせる。選択科目Ⅲには図を入れる。これらもおすすめです。採点基準の「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」に「コミュニケーション」があります。太字や図を上手に使うと、コミュニケーション項目で加点されるためです。
一方、迷信や、都市伝説になったテクニックもあります。集中力を高めるために、耳栓を持って行けというもの。これを信じて、私は、耳栓を試験会場に持っていきましたが、はっきりと「使用不可」と言われました。
また、選択科目Ⅱ-1や選択科目Ⅱ-2にも図を入れろという指導が。入れても構わないし、適切な図であれば加点も狙えますが、時間の制約が、より大きくなるというリスクが高まります。
図には、色鉛筆を使えと指導する参考書もありますが、これもあまり意味がないでしょう。実際、やってみて有効だったという合格者にあったことがありません。
皆さんは、自分に合ったテクニックをみつけて、受験に挑んでください。
2019年07月07日 作成 / 執筆:技術サムライ講師

試験が終わったら、必ず選択科目Ⅲの復元解答を作成します。なぜなら、選択科目Ⅲの答案は口頭試験のときに、試験官の手元にあるからです。
自分が書いた内容が不確かな状態では、それについて問われても、正しい応答ができないはずです。
ここで問題になるのは、試験終了直後に、復元解答を作る気力が残っていないことです。
そこで、多くの受験生は、次の日、そしてその次の日と、やるべき日を後に回していくのです。
当然に、記憶が曖昧になり、精度の低い復元答案ができてしまいます。
また、筆記試験の出来が悪く、自分では不合格と思っていても、合格している人がかなりいます。
合格発表があった後に、あわてて復元解答を作る人がいます。
もちろん、口頭試験で苦戦します。その復元解答は、まったくもって、不正確な文字情報だからです。
そこで、試験終了後、完全な復元解答を作る必要はない、と心理的ハードルを下げるのがおすすめです。
つまり、後日、復元解答を作るため、どんなことを書いたかを箇条書きで書くらいで良いとするのです。
そうすれば、後日、まったくのゼロから復元解答をつくるよりも、うんと効率がよくなります。
試験終了直後には、箇条書きで、キーワードだけでもよいでしょう。
帰りの電車の中でも良いですし、アルコールを飲みながらでもよいでしょう。
そのかわりに、毎日毎日、少しずつでも、そのキーワードに情報を補足していきます。
そのうち、こう書けばよかった、ああ書くべきだったということがでてきます。
それを、赤字でコメントを書いていくのです。
この赤ペンでの振り返りが、口頭試験での質疑応答に役立つのです。
2019年07月16日 作成 / 執筆:スチールマニア講師

受験生の皆さん、昨日の技術士試験お疲れ様でした。
原稿用紙9枚の記述は、さぞ疲れた事と思います。
酷使した手と精神を十分労わってください。
ただし、復元論文だけは、すぐに「必ず」作成しましょう。
その理由は、筆記試験の合否のどちらになっても復元論文が必要だからです。
なぜ合否に関係なく必要か、について以下に示します。
まず合格の場合です。
筆記試験に合格した場合は口頭試験を受験します。
口頭試験は、試験センターが配布した受験申込案内の9ページに次のように書かれています。
------------------------------------------------------------------
2.口頭試験
技術士としての適格性を判定することに主眼をおき、
筆記試験における答案(総合技術監理部門を除く技術部門については、問題解決能力・課題遂行能力を問うもの)
及び業務経歴を踏まえ実施するものとし、次の内容について試問します。
------------------------------------------------------------------
つまり、「筆記試験の答案及び業務経歴を見ながら質問しますよ」と書かれています。
よって、11月~1月の口頭試験で聞かれそうなことを事前に準備しておく必要があります。
そのために忘れないうちにしっかりと復元論文を作成する必要があるのです。
次に不合格であった場合です。
不合格の場合は、復元論文で来年の準備を開始します。
まず今日の解答が現在のあなたの実力です。
その復元論文を使って、これからどのような勉強をすべきか分析します。
知識が不足していたのだろうか? 文書表現が不足していたのだろうか?
質問に忠実に答えて無かったのだろうか? など分析するのです。
さて合否いずれにしても、復元論文が今後の貴方のスタートです。
復元論文をしっかり作って次のステップへ進みましょう。
復元論文の添削についても行います。
しかし、今の時点で合否を気にするのはナンセンスです。
私自身、とっても気になったので、皆さんが気になるのは当然かと思いますが。
2019年07月28日 作成 / 執筆:Lucky Ocean講師
受験生の皆様へ
7月に二次試験を受験して、その合格発表が10月。そして、口頭試験が11月末から始まります。今は少し中間的に気が緩む時期かもしれません。人間リフレッシュも必要です。しかし、リフレッシュする前に、答案の再現は完了しておきましょう。
エビングハウスの忘却曲線では、20分後には42%を忘れる。1時間後には56%忘れる。1日後には66%忘れる。すでに2週間ほど経過しているので、もう皆さんの記憶はごく僅かかもしれません。また、ほとんどの人はすでに答案の再現は済んでいるかもしれません。しかし、もしもまだならまだ間に合います。是非答案を再現しておきましょう。
なぜか?
それは答案を再現しておけば、記憶が定着します。今再現しておけば、10月の発表の時に復習して、口頭試験の直前に復習すれば、口頭試験で貴殿の答案のことを聞かれても、まごつくことはないでしょう。
本番の試験では、時間が限られています。緊張した中で貴殿の実力を100%発揮するのは難しかったかもしれない。しかし、今ならゆっくりとネットで参考情報を見ながらあなたが理想と考える回答を作ることも可能かもしれない。それは成長に繋がります。先日も再現論文を査読して欲しいと依頼を受けました。この姿勢は技術士として必要なものです。
より良き技術士になりたいのであれば、謙虚な気持ちと真摯な姿勢を貫きましょう。そして、10月に筆記試験の合格を確認できたら、次は
口頭試験の準備にすぐに着手しましょう。自分の場合は、Q&AのQを発表前に作っておき、発表が確認されてから必死にAを作りました。
時間は有限です。チャンスは何度もありません。是非、チャンスを活かして、合格をゲットして欲しいと思います。
以上
2019年08月06日 作成 / 執筆:スチールマニア講師

受験生の皆様、お疲れ様です。
私の方への筆記試験本番の論文添削の依頼も一段落したところです。
試験制度が変わり、初めての年なので、
なかなか採点基準や合格基準が明確化していないため、
他人の採点に一喜一憂する必要はありません。
受験生全員が自分の回答に不満がありますし、改善点があります。
完璧な答案だ、という人など一人もいません。
基本的には、何も書けなく答案用紙の8割を埋めることができなかった、
という人以外は、合格を信じて口頭試験の勉強に移ってください。
技術士に合格する為には、口頭試験は必須です。
いつか必ず勉強する必要が出てきます。
ならば、合格を信じて、今勉強するのがベストでしょう。
技術士2次試験は、難易度が高いと言われていますが、
合格率は部門により異なりますが、約10%です。
10%という数字は、そこまで小さな数字ではありません。
例えば、マラソン大会で5万人が参加するものがあったとします。
入賞する人は毎日何十kmと走っているアスリートであり、
一般人が入賞することは非常に困難です。
そして入賞は大きな話題となり、名誉が与えられます。
しかし、5000番内に入ることは一般の方でも可能性があります。
また5000番の方が話題になることは全くありません。
技術士試験は、1番、2番を決める試験ではないのです。
上位10%の範囲に入れば、全員が等しく技術士になる権利が与えられるということです。
自分の論文に自信がないと仰っている受験生もいますが、
他の方と比較しても、そこまで自信を失う出来ではありません。
不安はあるでしょうが、ぜひ前に進んでみましょう。
口頭試験は、暗記する項目もあります。
早く始めて悪いことなどありません。
頑張ってください。
2019年08月08日 作成 / 執筆:技術サムライ講師

技術士二次試験は、平成31年度(令和元年度)試験から択一式試験がなくなりました。そのため、筆記ばかりの試験になりました。つまり、以前のような知識を直接に問う設問がほとんどなくなりました。
しかし、必須科目Ⅰでも、選択科目Ⅱでも、選択科目Ⅲでも、依然として専門知識は基礎として必要です。なぜなら、論文を書くのにも、専門的学識を踏まえることが求められているためです。また、実際に、評価項目となるコンピテンシー(技術士に求められる資質能力)の1つに専門的学識も含まれているためです。
そこで専門知識の記憶をいかに効果的、かつ効率的に定着させるかテーマになってきます。
技術士試験は、原稿用紙に手書きする制度になっています。ですから、キーワードが正確に書けるように訓練しておくとよいでしょう。パソコンでまとめてばかりいると、簡単な文字も書けなくなってしまいます。
手で書くとき、丁寧に書くのがおすすめです。トメ、ハネ、ハライに気をつけて、はっきりとした字になるようにします。そうすることで、そのキーワードを目にする時間がわずかに長くなり、走り書きしたときよりも忘れにくくなります。
また、丁寧に書くことは、本番では必須です。丁寧に書けないが故に、合格点に至らないケースが多いのです。これは、悪筆の受験生が想像しているよりも深刻な現実です。
さて、一度書いたキーワードやその解説文は、24時間後、1週間後、1か月後というように期間を定めて見直しましょう。はじめのうちは、復習のインターバルをあまり空けずに、定着してくれば、多少の間を空けて見直すようにします。
そして、過去問で、そのキーワードを使って答案を書いてみましょう。
このように、「インプット→復習と定着→アウトプット」を一括りとして専門知識を定着させると良いでしょう。
2019年09月25日 作成 / 執筆:スチールマニア講師

7月以降、7月に実施された筆記試験のことを振り返ることをしたでしょうか?
再現論文を書く際に振り返りますが、回答しなかった問題については振り返りましたか?
私が受験した際には、回答に選択しなかった問題に関する質問はありませんでした。
しかし受験生の中には、回答しなかった問題に対して意見を聞かれる質問をされた方もいるようです。
口頭試験は加点方式なので、質問に答えることができなかったとしてもスグに不合格になることはありません。
しかし、すでに題目があり、調べれば回答が得られるものに対してスルーしてしまっては勿体無いと思います。
しかも、回答しなかった問題の模範解答を作成することは、
たとえ筆記試験に合格できていなかったとしても来年度の試験対策になるのです。
勉強して無駄になることはありません。
「効率的な勉強方法は?」とよく聞かれることがあります。
人によって効率的という意味は異なるでしょう。
私が思う効率的とは、あらゆる事象に役立つものから勉強することです。
例えば、必須問題と選択Ⅲの問題は回答方法も出題内容も採点内容も非常に似ていることが技術士会のHPを見れば明らかでした。
その場合は、選択Ⅱの試験勉強よりも、選択Ⅲと必須問題の模範解答から作っていきます。
また、幅広い問題を考えるのではなく、まずは過去問です!
明らかに過去問と類似した出題が多いことは分析をすればわかるでしょう。
口頭試験まであと2,3ヵ月です。
長いようであっという間に来てしまいます。
やるべきことは何があるか?
その中で優先順位はどうか?
これらを考えて実行することも、技術士として大事な要素だと思います。
2016年11月19日 作成 / 執筆:技術士システム【運営者】講師

平成28年10月18日の科学技術・学術審議会技術士分科会 第9回制度検討特別委員会において、技術士試験における変更が報告されました。
早ければ2018年度の試験から変更になります。
委員会が技術士制度の参考とした国際エンジニアリング連合会(IEA)が定める「エンジニア」には、資格取得段階で明白な解決策がないような複合的な問題を技術的に解決できる能力が求められています。日本の技術士にも同様の問題解決能力を求める必要があるとして、その能力をより的確に把握するには択一式より記述式の方が適しているとの委員会の判断で変更となりました。
主な変更点
1)必須科目を記述式に切り替える。
2)選択科目では専門知識及び応用能力を問う論文の記述枚数を現行の600詰め用紙4枚以内から3枚以内に削減することで、受験生の負担を軽減する。
ということは、来年の技術士試験に合格できなければ、2018年度からは必須科目が記述式になります。現行の試験方法で合格したければ来年の試験で合格するしかありません。
下記に具体的な試験方法の方向性を記載します。
■必須科目:
「技術部門」全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力
(記述式、600字詰用紙3枚以内、試験時間2時間、配点40点)
■選択科目1:
「選択科目」に関する専門知識及び応用能力
(記述式、600字詰用紙3枚以内、配点30点)
■選択科目2:
「選択科目」に関する問題解決能力及び課題遂行能力
(記述式、600字詰用紙3枚以内、配点30点)
※選択科目1.2合わせて試験時間3.5時間
(資料:文部科学省)
2017年01月12日 作成 / 執筆:【ニュース担当】eastwest665講師

技術士の電気電子部門は、電気工事士や電気主任技術者と比較されると、今一つ対外的な評価が低く見られがちです。
建設部門の技術士は、コンサル事業を行うために必要な資格とされているのに対して、電気電子部門の技術士は取得しても特別業務に従事できる内容が増えるというものではありません。
実際に、電気関係のコンサル事業は、必要な資格が法律的にあるわけではなく、電気主任技術者資格でも代替できるため、電気電子部門の技術士試験は受験者自体が少ない傾向にあります。
しかし、電気関係の建設工事を監理する際に、電気電子部門の技術士は、意外な形で活用することができます。
建設工事での請負金額が一定額以上の工事の監督をする場合、監理技術者という資格を持った現場監督が現場に常駐する必要があります。
この監理技術者の資格は、現場工事の経験年数で取得ができるのですが、この経験年数になるかどうかという審査基準がとても厳しく、人によっては10年間の現場工事の経験が必要となります。
電気工事の設計などを担当していると、こうした監理技術者資格を取得するのがとても難しく、現場監理の業務にも範囲を広げたいと考えている人にとっては、とても大きな障壁となっています。
しかし、技術士資格を持っている人は、該当部門の工事の監理技術者資格であれば、現場工事の経験に関わらず取得することが可能となります。
これは、電気工事士や電気主任技術者資格では認められていない資格取得要件となります。
技術士資格を取得すれば、工事監理も行うこともできるようになるのです。
工事設計と工事監理をセットでできる人間ともなれば、転職時にも有利となり、会社にとっては重宝されること間違いなしです。
電気工事を行っている会社に勤務されている設計担当の方は、是非電気電子部門の技術士取得を目指してみてはいかがでしょうか。
2017年02月25日 作成 / 執筆:【ニュース担当】eastwest665講師
技術士は、21の技術部門で構成され、それぞれの専門知識を活かした技術士たちが活躍しています。
技術系の大学を卒業して設計などの業務を行っている人であれば技術士の資格の名前は聞いたことがあると思いますが、具体的にはどのような人が受験をするのでしょうか?
・技術コンサルティングを行う人
技術コンサルティングとは、主に公共工事などで、計画を行うような業務を指します。例えば、国や県などがこの部分に橋をかけたい、道路を作りたい、公共施設を建てたいというような場合に、必要な材料や工事の期間、技術的な資料(橋であれば荷重や災害時に壊れないか等)の作成といった設計委託業務を発注します。
そういった設計委託業務を受注する技術コンサルティング会社に勤務するような人は技術士資格の取得は必須といってもいいでしょう。
会社によっては課長昇格の要件になっているようなところもあるようです。
・製造メーカで製品設計を行う人
製造メーカなどで設計業務を行う人は、工事などを行う人と比べて社外資格がなくても業務に当たれる場合が多いことから、資格取得を行わず何年も来てしまうといった人も多いようです。
そうした人も自分の技術レベルを対外的に証明できる資格として技術士が挙げられます。
製造メーカの設計は困難な案件を技術提案で解決したという事例が出やすい業種でもあります。
技術士2次試験で求められる実務経験としての経験を積みやすいと言えます。
技術士はその腕が認められれば、将来的に独立することも可能な資格です。
将来的なことも見据えて受験に取り組みましょう。
2017年03月13日 作成 / 執筆:タートル講師
前回に引き続き、勤務先における業務経歴のうち、「業務内容」の部分にテーマを絞って、注意点をアドバイスしたいと思います。
1つ目の注意点として、「計画、研究、設計、分析、試験、評価(又はこれらの指導)」という表現を入れ込みましょう、ということを書きました。
2つ目の注意点は、「仕事の特徴がわかるような記述」を心掛けましょう、ということです。
業務経歴は、受験要件を満たしているかを確認する事務的な資料でもありますが、大切なのは口頭試験の参考資料となるという点です。
筆記試験に合格したら口頭試験を受けるわけですが、試験官は業務経歴の業務内容の記載事項を見て、「この受験生はこういうキャリアを積んできたんだな」と情報を得たいはずです。
その時に、例えば
道路構造物の設計
コンクリート構造物の強度分析
という感じで、具体的な仕事の中身がわからない記述があったら、試験官はどのように思うでしょうか。
1つ目の注意点で書いた点はクリアしていますから、事務的には経歴としてカウントされるのは間違いありません。
しかし「技術士にふさわしい」業務なのかどうか、皆目見当がつきませんから、おそらく試験官は口頭試験で仕事の内容を逐一質問するのではないでしょうか。
口頭試験は原則20分間です。しっかりと受験申込段階で書いておけば受ける必要がない質問で時間を使うのは、大変に不利なことです。
例えば道路構造物の設計をしたのであれば、どのような構造物なのか、どのような道路種類だったのか、周辺状況はどのような所だったのか、技術的に課題となったことはどのようなことだったのか、等がイメージできるような記述をすることが大切です。
以上、2回に渡って「業務内容」をテーマに注意点を述べました。
事務的に問題ないのは当然として、口頭試験を意識して「技術士らしさ」が伝わるような書き方を心掛けましょう。
*受験申込に関して、別の視点からも投稿があります。併せて御覧ください。
*出願対策講座を行っています。講師ページからお気軽にお問い合わせください。
2017年05月03日 作成 / 執筆:Lucky Ocean講師

4月28日までに受験申し込みをした方へ
申し込みも完了し、受験モードがスタートしましたか?まだ、何をどうやればいいかよく分からないと言う方も多いかもしれませんね。
選択問題と記述問題でそれぞれ対応方法が異なります。
選択問題:これはまず過去問題にトライして、正解か不正解かを確認しましょう。そして不正解の問題だけまた解いてみましょう。選択問題は2−3度やると正解になる問題と、全くはの立たない問題があります。勉強の対象は当然ながら後者です。まずはこれを「マスターしたつもり」になるまでネット等で勉強したら、記述問題に集中しましょう。数週間したら、また選択問題にトライしましょう。前回ほどではないけど、不正解の問題があります。人間の記憶は忘却するようになっています。でも、忘却したものを再度記憶するという作業を2−3回行うと記憶が定着します。脳が、忘れたらいけないのだと気づくのです。でも、どうしても正解できないものがあるでしょう。それは試験当日の朝に答えを丸暗記して対処しましょう。私もそれで2問ほど正解できました(笑)。
記述問題:これはやはり自分の専門分野で重要なキーワードを100個ほど抽出して、その各キーワードに関して概要と、課題と、課題への対策を技術ノートとしてまとめましょう。これが勉強の王道です。そして、この技術ノートが一通りできたら、それを見ながらでも良いので、600字の原稿用紙に概要と課題と対策などを記述しましょう。A4の技術ノートには900字相当の情報量があるので、600字ならなんとか書けるでしょう。でも、書きにくい部分や、不足している部分、過剰な部分がきになるはずです。そのように気づいた点を加筆修正します。これを2−3度行うと、かなり洗練した技術ノートになるし、記憶にも定着します。
記述問題への対応:問題を見てすぐに書き出すのはダメです。まず、出題者の意図をくみ取り、例えば、機能と課題と対応策であればそれに関するキーワードを記載した表を作成しましょう。そして、その表に書いた内容を説明できるようにフレームワークを決め、そのフレームワークに沿って記述していきます。その場合にも、図表は有効です。字数制限の対象外でもあります。
参考)記述問題への対応フローはマイブログ(http://hiroshi-kizaki.hatenablog.com/#edit)に掲載しました。よければ参考にしてください。
2017年06月03日 作成 / 執筆:タートル講師
合格に繋がる論文とそうでない論文はどこが違うのでしょうか?
これまで多くの方の論文添削をしてきた中で、「ここが重要」と感じている点を述べたいと思います。
■問われていることに対して全て答える
問われていること全てに答えるなど当たり前すぎると思われるかもしれませんが、意外と出来ていない方が多いです。
例えば次のような問題が出たとします。
土砂災害対策を検討する上で考慮すべき災害の特徴を、近年の土砂災害の実態を踏まえて
2つ述べるとともに、それぞれの特徴に対応するためのハード・ソフト両面の対策につい
て留意点を述べよ。(平成25年度 建設部門 河川、砂防及び海岸・海洋科目)
ここでは、
・土砂災害対策を検討する上で考慮すべき災害の特徴その1(特徴1とします)
・土砂災害対策を検討する上で考慮すべき災害の特徴その2(特徴2とします)
・特徴1に対応するためのハード・ソフト両面の対策についての留意点(留意点1とします)
・特徴2に対応するためのハード・ソフト両面の対策についての留意点(留意点2とします)
を答えることが求められています。
こういう場合にありがちなのが、
・特徴1や特徴2を述べる際に、近年の土砂災害の実態を踏まえていない(ミス1とします)
・留意点1や留意点2が、ハード・ソフト両面についての記述になっていない(ミス2とします)
というようなミスです。
ミス1は、特徴1、2ともに「近年の土砂災害の実態を踏まえて」という前提条件をすっかり忘れているパターン、あるいは特徴1では近年の土砂災害の実態を踏まえているのに特徴2では出来ていない等のパターンがあります。
ミス2は、留意点1、2ともに「ハード・ソフト両面」という前提条件を忘れてハードかソフト一方しか書かれていないパターン、あるいは留意点1ではハード・ソフト両面の記述ができているのに留意点2では一方しか書かれていない等のパターンがあります。
こういうミスは、問題文を見て「これなら書ける!」とばかりに、いきなり論文を書き始めた場合に犯しやすいものです。
ごく簡単なキーワードだけでも良いので、何について記述するのか骨子を書いて、問われていることに全て答えているかどうかをチェックしたうえで論文を書けば、この手の失敗は激減するはずです。
*筆記試験対策講座を行っています。講師ページからお気軽にお問い合わせください。
2017年06月26日 作成 / 執筆:【ニュース担当】関口雄太講師
「頭をたくさんつかったから、甘いものが食べたくなったなぁ」と思ったことありませんか?高カロリーの食品を食べると勉強が手につかなくなるリスクがあります。
「グルコース」はブドウ糖の一種。頭や体を動かすためのエネルギー源となっており、適度に摂取する必要がある成分です。「技術士二次試験に向けてがんばるぞ!でも、なんだか体がだるくて勉強が起きない……」と悩まされた経験がある人も多いでしょう。とくに昼食や夕食を食べたあとの倦怠感で勉強する気がなくなってしまいがちです。食後は消化器官が活発になり、消化することにエネルギーを使用するため、多少の眠気は避けられません。ですが、とても強い眠気を感じるとき、それはグルコースの摂取の仕方に問題があるかもしれません。白米やお菓子など、糖度が高い食品を食べると血中のグルコースが急激に上昇。その結果、活動する気がなくなってしまうということです。
アメリカの裁判にまつわる言葉に「トゥインキー・ディフェンス」というものがあります。トゥインキーとはアメリカで大ヒットしていたお菓子の名前。とても甘く、いかにもアメリカらしい高糖度な食品です。なぜ、このトゥインキーが裁判に関係しているのかというと、1978年に話はさかのぼります。殺人事件を犯した容疑者が「糖分が多量に含まれるお菓子を食べたために、精神状態をおかしくし、殺人を犯した」という弁護士の主張が認められ、減刑されるということがありました。アメリカの陪審員制度が抱える問題点を指摘されることもあるこの事件ですが、糖分の多量窃取が精神に異常をきたすことが理解された事件とも言えます。つまり、人は急激に血糖値が上昇すると通常とは違う、暴力的で、自己コントロールできない状態になりやすいということです。
技術士二次試験の勉強中、グルコース不足でやる気がでないときはフルーツや野菜、食事であれば肉や魚から食べてじっくりとグルコースが体内に取り込んでいくことがよいとされています。自己コントロールは勉強だけでなく、仕事の人間関係も左右します。糖度が高いものに頼らず、健康的な自然の栄養を摂取するよう心がけてください。
2017年07月04日 作成 / 執筆:タートル講師
今回は、論文を書く・問題を解くと言った試験そのものに関する準備以外で、受験直前~当日にしておくべき様々なことを書きたいと思います。
ロジスティクス的なことをしっかりしておくことで、試験そのものに集中することができます。
1.受験票を準備しておく
受験票は手元にありますか?
当日持っていくのを忘れることは無いと思いますが、前日の夜中や当日の朝に準備をしようと思っていて、「あれ、見つからない!」となったら一大事です。
この記事を見終わったら、受験票がどこにあるのか必ず確認しておきましょう。
2.試験会場までの経路を確認しておく
技術士試験に限らず、試験開始直前になって大慌てで入室する受験生が必ずいるものです。
息は乱れて大汗をかいて、すぐには集中できないでしょう。周りの受験生に対しても迷惑です。
そうならないように、自宅から受験会場までの交通経路は必ず確認しておきましょう。Googleマップ等を使えば、自宅から受験会場までの交通経路を検索することができます。また乗換え等が複雑な経路の場合には、何番出口を使えばよいのか等も事前に調べておきましょう。大きな駅で出口を間違ったら、見当違いの方向に行ってしまうこともあります。
3.筆記用具を準備しておく
シャープペンシルは最低でも2本準備しておきましょう。1本だけ準備していて壊れたらおしまいです。シャープペンシルの芯も十分に準備していますか?芯がなければ単なる棒です。
鉛筆も何本か持っておいた方が良いでしょう。消しゴムも最低2つは準備しておきましょう。
4.身の回り品を準備しておく
会場によっては、エアコンの効きが悪い、あるいは効き過ぎて寒いということもあり得ます。これは行ってみなければわかりません。汗をぬぐうタオル、体を冷やす冷却剤、寒いときに羽織ることができる長袖シャツなどを準備しておきましょう。
また、文字を書き過ぎて、後半戦は指が痛くなるかもしれません。バンドエイドのような絆創膏を持っているといざと言う時に役立ちます。
5.昼食を準備しておく
昼休みは短いですから昼食を食べに行く余裕はありません。最寄りのコンビニは、食べ物が売り切れる可能性があります。
自宅から昼食を持参するか、自宅近くで昼食を仕入れてから会場に向かいましょう。
2017年07月24日 作成 / 執筆:Lucky Ocean講師

平成29年度技術士試験(二次試験・筆記試験)の択一式問題の正解が今朝ほど日本技術士会の
ホームページに掲載されました。次のURLからもアクセスできます。
https://www.engineer.or.jp/c_topics/003/attached/attach_3935_1.pdf
今年度の技術士試験を受験した人はぜひチェックしてください。
そして、次の対応をお願いします。
1)合否を確認する。
2)間違った問題をチェックする。
3)10月31日の合否発表に備える。
1)合否を確認する。
・自分が選択した問題とその回答を確認しましょう。
・技術士試験(一般部門)では、まずはここで60%以上であることが合格の条件です。
・もし、残念だった人は、自分の勉強方法が適切でなかったのかを振り返って、来年の
受験への戦略を立て直しましょう。応援するので、今回の悔しさを絶対晴らしましょう。
2)間違った問題をチェックする。
・選択した問題だけではなく、すべての問題に対して、正解だったのかどうかをチェックしましょう。
・正解ではなかった問題や分からなかった問題は、自分の知識の不足や理解違いを正す絶好のチャンスです。
・技術士に合格した後も資質を向上する努力は求められるし、必要です。
3)10月31日の合否発表に備える。
・択一式問題が合格レベルに達していた人はおめでとうございます。
・でも、技術士試験のメインは記述式です。こちらの合否発表は10月末だし、口頭試験も
通常12月ですのでまだ少し時間があります。
・記述問題の再現論文を完了した人は、技術士試験を忘れてみてはいかがでしょうか?
・夏を楽しむとか、溜まっていた仕事をこなすとか、家族サービスに努めるとか、海外旅行に
行くとか、今までとちょっと違うことにチャレンジしてみませんか?
以上
2017年07月14日 作成 / 執筆:【ニュース担当】eastwest665講師
技術士二次試験の口頭試験。
こう書くととても高度な内容のことを行っているように見えてしまいます。
実際には、事前に提出した業務経歴票を基に、あなたが技術士にふさわしいのかを試験する場です。
これは、会社に入社するための採用試験の最終面接と言ってもいでしょう。
言わば、技術士という会社に入社するための役員面接と言い換えることができます。
試験官からの質問内容も、業務経歴票で不明な点や、もっとも技術者として成長したと思えるエピソードなどの説明を要求されることもあります。
採用試験時に学生時代に頑張ったことなどを話した経験や、転職を経験されている方であれば、過去の会社での業務実績を説明したと思います。
それと全く同様です。
中には、技術士を取得しても現在の業務と関わりのないものも多いことから、「いまのあなたに技術士の資格が必要か?」と問われることもあるようです。
これは、入社の際に志望動機などを説明し、様々な質問をされて入社する動機が揺るぎないものなのかを聞かれた記憶のある方も多いのではないでしょうか?
こうした状況から技術士二次試験の口頭試験は、企業の最終面接とほぼ同じであるということが言えます。
技術士の口頭試験と難しい感じに考えずに、企業や官庁にお勤めの方であれば、誰もが一度は経験している採用面接を思い浮かべてみれば、試験の状況をイメージしやすいのではと思います。
転職をされている方は、過去の実績を面接官にアピールする経験をされていますので、口頭試験でも、あなたに対する知識が業務経歴票(履歴書)しかない試験官に自分をアピールする場を経験していますので、有利であるのではと考えます。
ただ一つ、違う点は、採用試験では入社後に上司となりうる人が面接をしているのに対し、試験官は技術士試験の時だけのお付き合いになります。
そう考えると、試験で行ったことが後々まで響くようなことはありませんので、気持ちを楽に持って試験に臨んでいただきたいと思います。
技術士の口頭試験までたどり着いたということは、それだけでも価値があります。
この最後の難関をなんとしてでも突破して、一生の宝となる技術士の称号を手に入れてください。
2017年08月25日 作成 / 執筆:【ニュース担当】関口雄太講師
学習の基本は「暗記」と「暗唱」の組み合わせですが、それぞれにかける勉強時間のバランスはとれていますか?暗記とは学習して脳に情報をインプットすること、暗唱とは覚えた情報を何らかの形でアウトプットすることを指します。もう少し技術士試験に照準を合わせて具体的に言うと、前者は教科書や参考書を開くことであり、後者は問題集を解くことです。この両軸によって私たち人間の脳は学習しているという意見に異論はないでしょう。
では、学習に欠かせないインプットとアウトプットのバランスはどの程度に保つと効果的なのでしょうか。どちらも大切であるし、わざわざバランスを考えなくても勉強の成果を上げることはできます。ですが、最適だと思われる時間の割り振りをすることで、短い学習時間をより充実したものに変えることができます。教育の現場でこのバランスについて研究した学者がいました。それが教育心理学の博士として歴史に名前を残したアーサー・ゲイツ(1890-1972)です。彼の名前は広く知られてはいませんし、日本語の書籍ではベネディクト・キャリー著『脳が認める勉強法』で紹介されるエピソードの一部として紹介されている程度ですが、重要な実験を行った研究者です。
ゲイツ博士はある学校のクラスを対象に暗唱の実験を行いました。文学作品に出てくる一説を暗記して、暗唱するというシンプルな実験です。その結果、学習効果を最大限に引き出すバランスが明らかになりました。全体の30%から40%を学習(インプット)の時間として使い、残りの時間を暗唱(アウトプット)の練習に使うことが最も適切だと発表しています。
ただし、ゲイツ博士の発見は学校の生徒を対象にした実験によるものです。高学年の生徒を対象にした実験ほど、インプットの時間は短い方が効果的だという結果になりましたが、成人の脳がまったく同じ学習バランスが最適とは証明されていません。また、個人差も当然あるでしょう。ですので、あくまでもインプットの学習時間が3割から4割を目安にして、自分に最適な学習時間を見つけていくとよいでしょう。
技術士システムでは過去の問題が用意されているので、インプットしたあとはストップウォッチや時計で時間を計りながらきちんと暗記できているかアウトプットの学習も行いましょう。インプットとアウトプットの両軸を鍛えることで、学習効果はアップします。
2017年10月11日 作成 / 執筆:Lucky Ocean講師
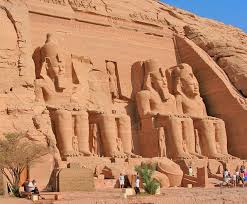
記憶は忘却するものです。有名なエビングハウスの実験によると、20分後に42%、1時間後に56%、1日後に74%、1週間後77%そして1ケ月後にはなんと79%が忘れてしまうという結果が出た。7月の技術士試験二次試験(筆記試験)が終わってから3ケ月近く経過している。エビングハウスの実験には含まれていないが、8割は忘れているでしょう!合格発表を受けてから回答を再現しようとしても、2割ぐらいしか覚えていないということでしょう(涙)。
試験直後に再現論文を作成した皆様は、もう一度読み返して、記憶を呼び返しましょう。もし、もし、もし、まだ再現論文を作成していない人は頑張りましょう。今回、伝えたいことは、二次試験(筆記試験)に向けて作成した技術ノートも有効だということです。これを読み返すと、多くのことを忘れてしまっていることにびっくりする方もいるかもしれない。正直、私も読み返して、どんだけ忘れているのかと驚きました。
また、スマホ等に技術ノートの内容を録音した人がいたら素晴らしい!これって効果的なのよね。私も、自慢ではないが、スマホに録音した技術ノートの内容を聞き返すと、綺麗に忘れていることばかりなので、逆に新鮮でした。脳は、不要な知識は忘れようとします。でも、一回忘れたものをもう一度思い出すと、脳はこれは覚えておかないといけないものと判断して、再現しやすいような領域に保存します。何度も何度も聞いていると、すぐに再現できるところに上書きしてくれます。つまり、これが記憶の定着ということなのです。
忘れた今がチャンスです。12月上旬が口頭試験だとすると、10月末に記憶を再現させた上で、11月末にも再度集中的に記憶を再現すると、12月の上旬には自信と余裕を持って口頭試験に臨めるようになります。試験は、残念ながら他人との比較の試験です。みんながまだスタートしていないこの時期に、半歩でも良いので、12月の口頭試験に向けて前進しよう!
そうすることで、一歩も二歩も人の先を行くことができます。10月31日の合格発表で、幸運にも合格だったけど、論文判定がBの人は要注意です。つまり、通常ならB判定は不合格だけど、論文判定は合計点なのでかろうじて合格した人です。口頭試験で狙われるはまずこの受験生です。そして、論文に対して何か補足はありますか?と聞いてくる可能性が高い。最後のこのチャンスをしっかりと活用して挽回してください。間違っても、「特にありません」とか、「忘れた」とか、「無言。。。」はダメです。不合格確定です。部門によって異なりますが、不合格の目安は2割です。この2割に入らないようにすることが重要です。
つまり、筆記試験がAA判定の人は、守りの戦略です。取りこぼしがないように入念に準備しましょう。筆記試験がAB判定やBA判定の人は攻めの戦略です。助け舟を見逃さず、リカバリーして合格の栄冠を手中にしましょう。
以上
2017年10月23日 作成 / 執筆:タートル講師
今月末(10月31日)は、技術士第二次試験の筆記試験合格発表です。
筆記試験に合格された方は、口頭試験に向けて準備を進めましょう。
ここでは個別の想定質問等の内容ではなくて、口頭試験受験の準備として心掛けたいことについてアドバイスしたいと思います。
1.必ず受験できるようにスケジュール調整等をする
技術士会のHPに明記されている通り、口頭試験の日時変更は一切できません。
したがって口頭試験の日時が確定したら、必ず受験できるようにスケジュール調整等をしましょう。
出張の予定を始め、様々な予定がある方もいるかもしれませんが、技術士の資格を手に入れたいのであれば、万難を排して受験できるように日程を調整してください。
また口頭試験は11月下旬から来年1月にかけて実施されます。特に12月以降は積雪による交通機関の乱れが起こっても不思議ではありません。積雪で飛行機や新幹線が遅れた
り止まったりしても、口頭試験の再受験はできません。また筆記試験から出直しです。前日は試験会場に徒歩でも行ける所に宿泊されることをお勧めします。
仕事等のスケジュール調整、悪天候による交通機関のトラブルというリスクへの対策も口頭試験の一環と考えましょう。
2.第三者に想定質問を作成してもらう
三義務二責務、業務経歴の紹介というような定番質問については、書籍やネット情報でも入手可能です。
しかし「業務内容の詳細」に関しては受験者一人一人で全く内容が異なります。したがって、「業務内容の詳細」に関する想定質問は各々で準備する必要があります。
この「業務内容の詳細」に関する想定質問は、第三者に作成してもらうことをお勧めします。
自分で作成、あるいは同僚に質問を作ってもらうのでは、業務の内容や経緯を知っているため、「甘い」問いになる可能性があります。
業務の内容や経緯を知らない第三者に質問を作ってもらえば、あなたが前提条件と思い込んでいた部分への切込みや、「ここはちょっと自信がない」という点をズバリ付く
ような厳しいものになるはずです。
*出願対策講座を行っています。講師ページから詳細を記したファイルをダウンロードできますのでご覧ください。
2017年10月26日 作成 / 執筆:【ニュース担当】関口雄太講師
「あとで、やればいいや」と思って、課題を先延ばしにしたことはありませんか?
5分間だけ、スマホのアプリで息抜き。それから勉強を始めても、学習計画通りに進むから問題はない。そう思って、スマホを触り始めると、5分だったはずが、10分、15分となってしまうことは、よくあります。また、せっかく勉強をはじめても、すぐに息抜きが必要になり、勉強に取り組んではスマホをいじるというサイクルを繰り返してしまう人も多いはず。そして、結果的に、計画はギリギリすべりこみで終わらせたり、睡眠時間を削って取り組むことになってしまう。もし、そんな負のサイクルに入ってしまっているのであれば、先送りの習慣を見直すべきです。
取り組むべきことを先送りにすると、弊害があります。これは、調査データでも示されており、ピアーズ・スティールの著書『ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか』に紹介されています。一つの例として、レポート提出前の学生のケースが紹介されています。レポート課題が出されてから、提出日までの期間に取り組むべきことが、仮に100個あるとしましょう。ここでの100とは、仮のものですから、たとえば「資料を集める」だとか「1章を書く」だとか、そういったことだと考えてください。1日あたり、5ずつ取り組めば、20日後には、無事に100に到達します。しかし、先延ばしをする習慣があると、最後の5日間で、1日あたり20ずつ取り組むような事態になりがちです。本来であれば、4日かけて取り組むことを、1日でやるわけですから、クオリティも下がりますし、大慌てで取り組むので、気持ちは常に焦った状態になっています。もちろん、なかには課題にさく時間が十分ではないため、終わりきらない場合もあります。課題の取り組みを先延ばしにした学生は、最終的な仕上がりも、コツコツ取り組んだ学生と比較して、程度が低いものという調査結果が出ています。
この結果からわかるように、取り組むべきタスクを先延ばしにすることは、精神的な負担が大きいばかりでなく、最終的な成果物のクオリティを下げることになります。試験学習でいえば、クオリティの低下とは、つまり試験に通過できないということです。しかし、先延ばしは甘えではなく、習慣に問題があります。習慣を改善すれば、先延ばしグセをよい状態にすることは可能です。次回からは、先延ばしする習慣を改善するために紹介されている、具体的なアイデアを確認していきます。
2017年10月29日 作成 / 執筆:技術屋NR講師
前回に引き続き、口頭試験の準備として最優先にすべき「自分しかできないこと」についてお話したいと思います。
第2回は、「業務内容の詳細の見直し」についてです。
★業務内容の詳細の見直し
このサイトをご覧の方は、皆さんいろんなところから口答試験の情報を入手していて、受験申込の時に提出した「業務内容の詳細」について説明させられることはご存知のことと思います。
しかし、初めて二次試験を受ける方の中には、受験申込時に、口頭試験のことまで考えて書かなかったという方も居られるのではないでしょうか。私が初めて二次試験を受けた時もそうでした。
口頭試験では、「自分は技術士としてふさわしい業務を行ってきた」ということをアピールしなければなりません。
では、「技術士としてふさわしい業務」とはどういうことでしょうか。
「技術士」は国家資格なので、その答えは、法律、つまり、技術士の資格について定めた「技術士法」に書かれています。
「技術士としてふさわしい業務」とは、第一条、第二条の条文より、「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務であり、科学技術の向上と国民経済の発展に資するもの」ということになろうかと思います。
受験申込の際に作成した「業務内容の詳細」に、このような観点が抜けていれば、口頭試験の際に、それを補うような説明をする必要があります。
「業務内容の詳細」に書いたことは変えずに、「技術士としてふさわしい業務」であることをアピールできるような説明ができるようにしておいて下さい。
皆さん、頑張って下さい。応援しています。
「口頭試験の準備、まずは...(第1回) 筆記試験の再現」、「口頭試験の準備、まずは...(第3回・最終回) 説明した業務の振り返り」、もご参照下さい。
<ご参考>
技術士法
(目的)
第一条 この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
2017年12月12日 作成 / 執筆:【ニュース担当】関口雄太講師
ふとんに入ってからすぐに眠りにつけていますか?30分以上目がさえてしまって入眠できないという人は、入眠障害かもしれません。前回は睡眠不足の対処法について紹介しました。今回は眠れないときに対策を確認していきましょう。
普段からすぐに眠りにつけない人でも、だいたい何時ごろに眠りに落ちているか感覚はあるはずです。たとえば、12時ごろふとんに入ったけど、2時ごろ眠りについていると感じているとしましょう。その場合、なかなか寝付けないからといって、ふとんに入る時間を11時にしたり、10時にしてもあまり意味がありません。ふとんに入る時間を無理にはやくするのではなく、眠る時間にあわせてふとんに入りましょう。
いつも2時ごろに眠くなるという人であれば、2時まではリラックスタイムです。このとき、パソコンやテレビをつけてはいけません。暖かいお湯を飲むなどしてゆったりとした時間を過ごしましょう。もちろん、スマホをいじるのもよくありません。そして、いつも眠りにつく2時ごろに布団へ入るのです。これを習慣にしていくと、徐々に眠くなる時間が早くなってきます。2時に眠くなっていたのが1時30分ごろ眠くなり、1時になり、12時になるという具合に改善が可能です。
リラックスタイムには、ヨガや瞑想といった心を落ち着かせるような時間の過ごし方がオススメです。ヨガにもいろいろな種類がありますが、「陰ヨガ」というリラックス効果を高める効果があるヨガもありますから、うまく活用しましょう。このときにスマホやパソコンなどでヨガの動画をみてしまうと、どうしても光の刺激を受けてしまいますから、事前に覚えておくか、紙に書くなどしておきましょう。あまり型にこだわりすぎないことも大切です。
眠れないときの対策を上手に活用して、技術士試験に万全の体調で挑みましょう。
2017年12月14日 作成 / 執筆:【ニュース担当】関口雄太講師
睡眠時間はたっぷりとっているはずなのに、なぜか日中に眠くなってしまいませんか?睡眠時間が十分にとれているのに、眠りたりないと感じるのは、熟睡ができていないからかもしれません。
睡眠に必要な時間は人によってさまざまです。3時間も眠ればスッキリと起きられる人もいれば、10時間は眠らないと寝たりないという人もいます。睡眠が人間の脳に与える影響は研究途中ということもあり、睡眠にまつわる本はいまだに出版が続いています。最近の研究では、最適な睡眠時間の改善は難しいと考えられており、いままで10時間の睡眠がちょうどよかった人が3時間睡眠に切り替えるのは適切ではないとされています。
その上でぜひ覚えておいてほしいことは、睡眠時間は長ければいいとは言えないことです。たくさん眠れば頭がスッキリするわけではありません。なぜなら、熟睡している状態での睡眠が大切だからです。睡眠時間はきちんと取っているのに眠気が残る場合は、睡眠の深さが十分ではない可能性を疑ってみましょう。
睡眠の深さを改善するためには、寝る前の習慣を見直すことが大切です。まず、スマホです。スマホなどから発せられている「ブルーライト」と呼ばれる明かりは脳を目覚めさせてしまうため、就寝前には最適ではありません。できるだけ避けましょう。カフェインやアルコールの過剰摂取も睡眠を浅くする原因になるので、気をつけてください。
それだけでなく、軽度のフットワークを入れるとよりよい睡眠をとることができます。夕方の18時や19時ごろに、ジョギングやウォーキングなどの軽い運動を取り入れてみましょう。適度な疲労感はよりよい睡眠をつくります。
昼間、眠くなってしまう場合は就寝前の過ごし方を見直してみましょう。ちょっとした工夫が、よりよい睡眠をつくります。
2017年12月23日 作成 / 執筆:Lucky Ocean講師

人工知能の世界のキーワードに「過学習」という言葉があります。
最近の人口知能のアルゴリズムでは機械学習が注目を集めている。この機械学習は人間の頭脳の仕組みを参考にコンピュータに適用できるように工夫した学習方法だ。最近では、Alpha Goがプロの棋士を負かしたので有名になった。この機械学習で陥りやすいのが過学習だ。これは例えば囲碁の指し方を学習しても、表面的な指し方を学習してしまって、本質的な理解が深まらないという失敗の構図だ。
例えばゴルフでも、練習場では上手に打つのに、実際のゴルフ場では全然ダメなことがある。模擬問題は100点なのに本当の試験では及第点も取れないことがある。一方、練習ではそこそこだけど本番では最高の成果を残す人もいる。本番に強い人と、本番に弱い人の差は何が原因なのか。
それが過学習で説明できる。例えば、技術士試験の選択問題を何度もなんどもやっていると、本質的な理解ではなく、問題の順番で回答の番号を覚えてしまうことがある。この問題の答えは②とか、この答えは①とか。覚えるつもりはなくても、何度もやると覚えてしまうので、正解となる。マスターしたような気持ちになる。この錯覚が過学習という現象だ。本質を理解していないので、設問の構成や回答の選択肢が変更されるとまったく太刀打ちできない。
では、どうするのか。そのためには、学習の間隔をあけて、わざと忘れることだ。回答の番号といった意味のない情報は短期間のメモリー領域には保存されるが、長期間のメモリー領域には保存されない。したがって、一度学習したら、少し時間をあけて、もう一度トライする。その時に正解できたものは実力だ。その時に正解できなかったものは、やはり本質を理解していなかったということだ。なぜ正解できなかったのかを考えて、反省して、知識を補充して、理解を深める。そうすることで脳内の長期間のメモリーに保存できる。しかも、関連情報も増えているので、記憶の再現がしやすくなるという効果もある。そして、また時間を空ける。そして同じことをする。これを三回繰り返すと人間の脳の深いところに必要な情報が刻み込まれる。
そして、技術士試験の本番のタイミングに記憶と理解度のピークを持っていくのです。
私は、技術士の二次試験を三回受けました。その度にこのマジックナンバーの3を使った学習法を活用して、それぞれストレートで合格しました。ただ、面白いのは、例えば口頭試験で、3つの義務と2つ責務を覚えるが、見事に忘れていることだ。でも、一度理解して覚えているので、再度記憶領域に呼び返すのが非常に楽だ。一流の技術士を目指すのであれば、ダブルホルダーではなく、トリプルホルダーを目指すぐらいでちょうど良いのかもしれない。
頑張ってください。栄冠はあなたのものです。
2018年02月21日 作成 / 執筆:タートル講師
技術士第二次試験のスタートとなる受験申込に向けて、業務の棚卸を進めている方も多いと思います。
受験申込書の中で、口頭試験において特に重要な役割を果たすのが、720字以内で記載する「業務内容の詳細」です。業務内容の詳細を記述する欄には、『当該業務での立場、役割、成果等』と書かれていますが、それ以外に具体的に何を書くのかは指示事項がありません。
立場、役割、成果は当然記載するとして、それ以外に何を記載するのが良いのでしょうか?
多くの方は問題点や課題、課題を解決するための提案などを記載されていると思います。それでは『「現時点における評価」や「今後の展望」』(以下、評価・展望とします)を記載する必要はあるでしょうか?
評価・展望の記載は、取り上げる業務の内容や部門によって必要性が異なると考えます。
技術士法第2条では、『科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務』と、技術士の定義があります。
これらのうち、計画、設計等の業務を取り上げる場合には、評価・展望を記載する必要性は低いと考えます。
例えば砂防基本計画の立案であれば、次工程は施設設計です。橋梁設計であれば、次工程は橋梁の施工です。
このように、成果の次工程が概ねわかっている業務であれば、評価・展望を記載する必要性は低いはずです。建設部門や上下水道部門などは、こちらに相当するケースが多いのではないでしょうか。
一方、研究、分析、試験等の業務を取り上げる場合には、評価・展望を記載する必要性は高いと考えます。
研究、分析、試験の結果というのは、それらがどのような影響を与えるのか、どのように応用されていくのかという部分が非常に重要なはずです。「興味本位の研究」で、他への応用が示されないようでは技術士にふさわしいとは言えません。
このように、成果をいかに応用できるのかが重要な業務であれば、評価・展望を記載する必要性は高いはずです。機械部門や電気電子部門などは、こちらに相当するケースが多いのではないでしょうか。
以上、業務内容の詳細について、評価・展望を記載する必要性を述べました。
なお、ここでは業務内容の詳細に、評価・展望を文章として記載する必要性について論じています。口頭試験で試験官から「現時点でこの業務をどのように評価しますか?」、「今後、この業務の成果はどのように活用されるのか展望を述べてください」というような質問を受けた時には、記載の有無に関わらず答えることができるよう準備が必要なのは言うまでもありません。
*出願対策講座を行っています。講師ページから詳細を記したファイルをダウンロードできますのでご覧ください。